予防救急ガイドブック〜自宅でできる予防〜(高齢者向け)
- ID:4238
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
高齢者の方向けの予防救急ガイドブックを作成しました
救急車を呼ばなくてはならないような病気や、けがをしないよう、日頃から注意し心がける意識や行動を「予防救急」といいます。
救急車で搬送される事例の中で、高齢者に起こりやすい事故は「ほんの少しの注意」で防げることがあります。
事故予防の意識を高めていただくことで、病気や、けが等を未然に防止し、ご自身や大切なご家族が安全で健やかな生活を送っていただきたいという願いから「予防救急ガイドブック」を作成しましたので是非ご活用ください。
予防救急ガイドブック〜自宅でできる予防〜(高齢者向け)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
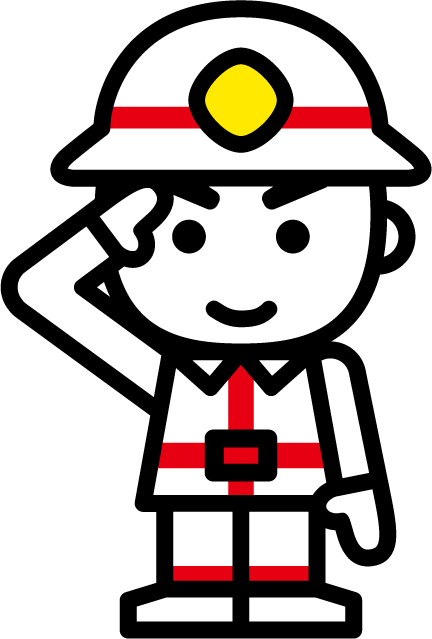
お問い合わせ
城陽市消防署救急課電話:0774-52-0697(救急情報サービス用電話)

